起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation:OD)を抱える方やご家族にとって、「水分をしっかりとること」はよく聞くアドバイスの一つですよね。ですが、実は「睡眠時間」が水分バランスにも深く関わっていることをご存知でしょうか?
今回は、米国と中国の成人を対象にした大規模調査からみえてきた睡眠不足と脱水の意外な関係が面白かったので紹介しつつ、ODと水分、そして睡眠の関係について考えてみたいと思います。
睡眠が短いと、脱水しやすい
アメリカと中国で合計2万人以上の成人を対象に行われた研究で、1晩の睡眠時間が6時間未満の人は、8時間眠っている人に比べて、尿が濃く、体が軽度の脱水状態になっている可能性が高いという結果が出ました 。
この研究では、参加者の尿中に含まれる「尿浸透圧」や「比重」などの指標を使って、体内の水分状態を評価しています。
尿浸透圧:尿の濃さを示す指標。高いほど尿が濃く、脱水傾向を示す。
比重:尿の重さを示す指標。高いほど尿中の溶質が多いことを示し、脱水傾向を示す。
すると、睡眠時間が短い人ほど尿浸透圧・比重が高く、つまりは脱水のリスクが上昇していたのです。
研究者たちは、この現象の背景には「抗利尿ホルモン(バソプレシン)」の分泌リズムが関係していると考えています。バソプレシンは、体内に水分を保持する役割を担っているのですが、睡眠が短くなるとこのホルモンの分泌が十分に行われず、結果として脱水に傾きやすくなるというのです。
起立性調節障害と水分バランスの深い関係
ODの症状─立ちくらみ、動悸、倦怠感など─は、体内の水分量と深い関係があります。OD患児でれば、「血液量の不足が根本的な原因の一つ」と指摘され、「1日2〜2.5Lの水分補給」をお医者さんから推奨された方がほとんどだと思います。
つまり、睡眠不足が脱水を引き起こす→OD症状が悪化するという、負の連鎖が起きてしまう可能性があるのです。
子どもの「夜更かし」に要注意
ODを抱える中高生には、睡眠リズムの乱れがあることも少なくありません。夜遅くまでスマホを使っていたり、昼夜逆転してしまっていたりする子も多いでしょう。
起立直後の低血圧(INOH)など、起床時にふらつきや気分不良が強く出るタイプのODでは、前日の睡眠と水分補給が大きく関係している可能性があります。
できることから始める:3つの予防ポイント
OD症状を少しでも和らげるために、以下のポイントを心がけてみてください。
1. 毎日7〜9時間の睡眠を目指す
起床・就寝時間をできるだけ一定にし、睡眠の質と量を確保しましょう。
2. 朝起きたらまずコップ1杯の水を
夜間の水分ロスを補うことで、朝の立ちくらみや気分不良を予防できます。
3. 寝る前のカフェインやスマホは控える
メラトニン分泌を妨げず、自然な眠りを促す環境を整えましょう。
おわりに
「睡眠」と「水分」。一見、別々の健康習慣のように思えるこの2つが、実は密接につながっているという発見は、ODと向き合う私たちにとって大きなヒントになります。
「ただ寝ているだけ」でも、体の水分調節は働いている──この体のしくみに目を向けることが、症状の改善につながる第一歩になるかもしれません。
ぜひ今日から、「よく眠ること」と「しっかり水分をとること」を意識してみてくださいね。

ではまた!
Rosinger AY, et al. Short sleep duration is associated with inadequate hydration: cross-cultural evidence from US and Chinese adults. Sleep. 2019 Feb 1;42(2). doi: 10.1093/sleep/zsy210. PMID: 30395316.
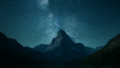

コメント