「夜、むしろ頭が冴える」問題
「布団に入っても眠れない」「夜になると頭が冴えてしまう」
これは、起立性調節障害(OD)を持つ多くの子どもたちや保護者からよく聞く声です。
実は、ODの睡眠障害は二次的な障害という位置付けではありますが、OD患児の半数近くがサーカディアンリズムが乱れていることが知られています。つまり、本来はリラックスして眠りにつくべき夜に、交感神経活動が高まっており、身体が“戦闘モード”になってしまっているのです。
本来は、夜間に「副交感神経」が優位になるはずですが、「交感神経(緊張神経)」が優位になってしまい、頭が冴えたり、活動モードが続き、寝ないといけないと分かっていても、眠気が皆無といった状態になってしまうんですね。
こんな状態では、布団に入っても脳も身体も“休め”のサインを受け取れず、睡眠の質も悪くなりがちです。
「腹式呼吸」と「観察」で交感神経を鎮める
Wang Shu-Zhenらの研究(2010年)では、22名の被験者に対して、「ゆっくりとした腹式呼吸(6回/分)」と「バイオフィードバック(自分の呼吸や心拍の状態を見ながら調整する方法)」を組み合わせたトレーニングを行ったところ、次のような効果が確認されました。
• 心拍変動(HRV)の改善
• 迷走神経の活性化
つまり、このような呼吸トレーニングは、迷走神経(副交感神経)を活性化し、交感神経の過剰な興奮を抑える効果があることが示唆されました 。
迷走神経ってなに?
迷走神経は「副交感神経」の中心(7割程度)ともいえる神経で、呼吸や心拍、消化などを穏やかに保つ働きをしています。腹式呼吸をゆっくり行うことで、この迷走神経が刺激され、心も体もリラックスしやすくなるのです。
特に、息を「吐く」時間を長くすることがポイント。吐くときに迷走神経がより強く働くため、心拍数が自然に落ち着き、安心感が生まれます。
今夜からできる!呼吸ワークのすすめ
ODで睡眠障害に悩む方には、以下のような腹式呼吸を毎晩のルーティンに取り入れることをおすすめします。
1. 寝る前に静かな部屋で横になる
2. 鼻から3~4秒かけてゆっくり吸う
3. お腹がふくらむのを感じながら、口から6~7秒以上かけて吐く
4. これを5分~10分程度続ける
研究では1分間に6回のペースを10分間行われていますが、細かいことはあまり気にせず、ゆっくりとした呼吸で、お腹の動きを観察しながら、吐く息を長めに!してみましょう。
前回の腹部を温める方法とあわせて、下腹部にあずきのちからを置きながら、呼吸による腹部の動きを観察するのが有効かもしれません。
「気のせい」や「怠け」「生活習慣が悪いから」と片付けられがちなODの睡眠障害。しかしその背後には、はっきりとした身体のメカニズムがあります。腹式呼吸は、薬を使わず、自分で自律神経を整える介入方法です。
ぜひ、就寝前のルーティンにして、自身の脳に「休む時間だ」と覚え込ませてみましょう。
ではまた!

Wang Shu-Zhen et al. (2010), ʻEffect of slow abdominal breathing combined with biofeedback on blood pressure and heart rate variability in prehypertensionʼ, Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(10), 1039–45. doi:10.1089/ acm.2009.0577.
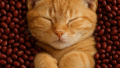
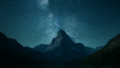
コメント