朝、なかなか起きられない。登校できても授業中にふらついたり、集中できなかったり。そんな毎日を過ごす起立性調節障害の子どもたちにとって、「どうすれば少しでも楽に過ごせるか」「日々の生活の質=QOLを高めるには何ができるのか」は大切なテーマです。
そこで、今回おすすめしたいのが、「読書」です。
ほんとにしんどい時は本なんて読めたもんじゃない!と思うかもしれません。たしかに、脳血流が低下した状態では、頭がぼーっとしたり(ブレインフォグ)、目が霞んだり、集中できずに思考がまとまらないでしょう。もちろん、そんな時は無理をして読む必要はありません。でも、体調のよいタイミングで、好きな本に触れることは、心身の健康にじんわりと効いてくる、メリットだらけの介入方法になり得ます。
読書の効能を示した2つの研究
なぜ「読書」がODの子どもたちにとって有効なのか?その理由を、2つの興味深い研究をもとに紹介します。
①「読書に熱心な子どもは精神的幸福度が高い」―National Literacy Trust(2018)
イギリスの教育慈善団体「National Literacy Trust」が2018年に行った大規模調査によると、「読書に積極的な子どもほど、精神的な幸福度が高い」との結果が出ています。
この研究では、読書をする頻度やその意欲が高い子どもたちは、自尊感情やポジティブな気分、自己効力感(=自分はできると思える感覚)も高い傾向にあると報告されています。
この研究では、因果関係までは分かりません。
しかし起立性調節障害の子どもたちは、体調不良によって「自分はダメなんじゃないか」「みんなに迷惑をかけている」と思ってしまうことがあります。そんな中で、物語の世界に没入することで「安心」や「共感」を得られ、自分の気持ちを整理したり、前向きな視点を取り戻したりできることがあるのです。
②「たった6分間の読書でストレスが68%軽減」―サセックス大学(2009)
もう一つの研究は、サセックス大学(イギリス)による2009年の研究結果です。
この実験では、参加者のストレスレベルを計測しながら、いくつかのリラクゼーション手法を比較しました。その中で最も効果が高かったのが「読書」。なんと、たった6分間本を読むだけで、ストレスが68%も軽減されたという結果が出たのです。
ストレスはODの症状を悪化させる要因のひとつ。特に「明日ちゃんと登校できるかな」「起き上がれなかったらどうしよう」といった不安やプレッシャーは、交感神経を高ぶらせ、自律神経による調節の不安定さを引き起こしやすくします。
読書は、そんな緊張をやわらげる効果的な“ストレスコントロール”手段にもなるのです。
読書のすすめ方 ― 無理なく、楽しく、自分らしく
もちろん、「活字を読むのがつらい」「頭がぼーっとして集中できない」日もあります。そんなときは無理しくて良いです。②の研究からわかるのは、たった6分で効果があるということ。読まなくてはいけない!などと考えず、あくまで面白いと没頭する時間こそが重要なんだと考えましょう。
以下のような工夫がおすすめです。
●夜寝る前に好きな本を少し読む。をルーティン化してしまう
● 家族や友人、先生と読んだ本について話す時間をもつ
小さな“できた”が、心と体の回復への第一歩
ODの治療は、薬だけでなく、生活リズムや心のケアも含めた「全人的なアプローチ」が求められます。
読書は、体力をほぼ使わずにできて、心に“栄養”を与えてくれる貴重なツールです。ストレス軽減、情緒の安定、自己肯定感の回復など、さまざまな角度からQOLの向上につながる可能性を秘めています。
「今日は学校に行けなかったけど、本を1ページ読めた。」
その経験が、明日の“ちょっとした前進”につながるかもしれません。
どんな本がおすすめ!?
いろんなジャンルの本を読めばいいと思います。小説は没入感や追体験を与えてくれますし、実用書や化学書物では、今の生活に役立つ方法を教えてくれるかもしれません。ただ今回は、小説を進めたいなと思います。
小説:自分が面白いと思える小説は、没入感を与えてくれます。何かに没頭している間は不安やプレッシャーから解放される貴重な時間です。また、小説といっても「愛とは何か」「人生とは何なのか」「死とは何か」など色んな哲学的テーマを持っている事が多いので、本をテーマから探してみてもいいでしょう。さらに物語には主人公の苦悩や葛藤が描かれており、人生の追体験という意味でも人生のヒントが見つかるかもしれません。
個人的に太宰治の「人間失格」は凄い本だなと思います。まず、引き込まれる文章ですし、内容としても、一見すると周囲が羨む充実した人生を送っていそうな人間も、内なる葛藤を抱えていて、もがいている様子は、過剰適応性格傾向のある方には共感できる部分も大いにあるのではないかと思います。
ではまた!

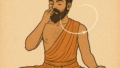
コメント