ODと睡眠の関係
起立性調節障害(OD)は、自律神経が正常に働かず、血圧調整や心拍数のコントロールがうまくできないことで起こる疾患です 。その結果、起立時に脳への血流が低下し、立ちくらみ、めまい、頭痛、倦怠感などの症状が現れます。
そんなOD患児には睡眠障害が多く見られます。ただし、これはODの直接的な原因ではなく、ODに伴って生じる「二次障害」としての睡眠の乱れであると考えられています。つまり、睡眠障害がODを引き起こすわけではなく、また睡眠を改善したからといってODが完治するわけではありません。
それでも、OD症状の改善を図るうえでは、自律神経の観点からも睡眠障害を改善し睡眠の質を向上させることは非常に重要だといえるでしょう。
なぜODの人は睡眠が乱れやすいのか?
日中の症状の影響や、自律神経失調が睡眠リズムに悪影響を及ぼします。主な要因として以下のようなものが考えられます。
(1)自律神経の乱れ
一般的には、朝から昼にかけて交感神経が活発に働き(活動的)、夕方から深夜にかけて副交感神経が優位に働きます(休息・回復)。しかし、OD患児では、朝に交感神経が十分に働かないことで起床困難になったり、夜になっても副交感神経が十分に働かず、むしろ交感神経活動が活発になることで、リラックスできず、入眠困難や中途覚醒を引き起こすことが考えらえます。
(2) 昼夜逆転しやすい
朝起きるのがつらいため、昼まで寝てしまうことで、上記の自律神経の日内変動リズムが狂い、夜に眠れなくなる悪循環が生じる。
(3) 日中の活動量低下→睡眠圧が不十分
睡眠圧とは、簡単にいうと眠りたい欲求のことです。日中の活動によって疲労が蓄積し眠りたいという欲求が生じますが、OD患児では活動を始める時間が遅いことや、日中の倦怠感が強く、体を動かす機会が減ることで、夜になっても十分な眠気が訪れないことが考えられます。
(4) ストレスや不安
OD症状が深刻な場合、学校や社会生活への影響も大きいため、心理的ストレスが蓄積し、睡眠の質が低下します。ODの症状が続くことで、「また明日も調子が悪いかも」と不安になり、寝つきが悪くなる。ストレスや不安も交感神経を刺激してしまう要素ですので、不安対策は睡眠改善の重要な戦略だと言えます。
睡眠を改善することのメリット
睡眠改善でODが完治するわけではないと冒頭で述べましたが、睡眠を整えることで以下のようなことが期待できます。
(1) 自律神経のリズムが整いやすくなる
(2) 日中の倦怠感が軽減
(3) 体内時計のリズムが正常化
今回の内容をまとめると以下のようになります。
・ODの睡眠の乱れは「二次障害」であり、睡眠を整えてもODが治るわけではない。
・しかし、睡眠を改善することで、自律神経の安定や日中の倦怠感の軽減が期待できる。
・生活リズムを整え、運動やリラックス習慣を取り入れることで、睡眠の質を向上させることが重要。
ではまた!

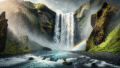
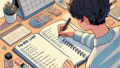
コメント