「朝起きられない」「学校に行けない」
そんな子どもを見て、「甘えてるだけじゃない?」と思う人もいるかもしれません。しかし、起立性調節障害(OD)を患う子どもたちは、むしろ“がんばりすぎた”結果として、体が壊れてしまっていることが多いです。
今回は、ヘルベルト・フロイデンバーガーらが提唱した「燃え尽き症候群の12段階モデル」を紹介しながら、OD患児に多い「過剰適応」や「成績優秀な子」の性格特性が、どう関係するのかを考えたいと思います。
燃え尽き症候群とは?
燃え尽き症候群(バーンアウト症候群)は、主に医療者や教師、介護士など「人のためにがんばりすぎる」職業に多く見られる精神的疲弊ですが、子どもにも起こります。
特にODの子どもたちは、もともと責任感が強く、期待に応えようと無理をしてしまうタイプ(過剰適応)が多く「見えないストレス」を内にため込みやすいのです。
限界を迎えるまでの12段階
以下は、燃え尽き症候群の12段階のプロセスです。ODの子どもたちは、このプロセスを“静かに・気づかれずに”たどることがあります。
① 承認欲求 (Compulsion to Prove Oneself)
→ 過剰な野心や完璧主義が背景にあり、周囲からの承認を得ようと過度に努力する段階です。自分の能力を証明するために、仕事や活動に没頭し、無理な要求も引き受けてしまいます。
例:いい子であろうとがんばる。「もっと努力すれば、親も先生も喜ぶ」と信じて疑わない。
② 努力の強化 (Intensified Exertion)
→ 承認欲求を満たすために、さらに努力を強化する段階です。仕事量が増え、時間を惜しまずに働くようになります。休日返上や残業も厭わず、自分の限界を顧みなくなります。
例:疲れていても手を抜かない。テスト前は夜遅くまで勉強。クラブ活動も全力。
③ 欲求の無視 (Subtle Neglect of Needs)
→ 睡眠、食事、運動、社会活動などの基本的な欲求やニーズを無視し始める段階です。休憩を取ることやプライベートな時間を削り、仕事や活動を最優先するようになります。
例:遊びや休憩も我慢。眠くても睡眠を削る。疲れやめまいを「気のせい」と切り捨てる。
④ 対立の抑圧 (Displacement of Conflicts)
→ 自身の問題や不満、内的な対立を抑圧し、無視する段階です。ストレスの原因と向き合わず、問題を外部に転嫁したり、責任を他者に押し付けたりすることが増えます。
例:体が限界でも、「大丈夫」と言い張る。「迷惑をかけたくない」という思いが強い。
⑤ 価値観の改変 (Revision of Values)
→ それまで重要視していた趣味、友人関係、家族といった個人的な価値観が軽視され、仕事や活動が唯一の価値基準となる段階です。仕事以外のことへの関心が薄れ、他者との交流も減ります。
例:自分の感情や趣味より、「評価されること」「成果を出すこと」がすべてに。
⑥問題の否認 (Denial of Emerging Problems)
→ 疲労やストレスの兆候、仕事のパフォーマンス低下など、燃え尽き症候群の初期症状を否認する段階です。問題を認めず、「大丈夫だ」「まだやれる」と自分に言い聞かせ、無理を続けます。
例:めまい、動悸、朝の不調があっても「気のせい」「甘えている」と自分に言い聞かせる。
⑦ 引きこもり (Withdrawal)
→ 社会的な交流から引きこもり、孤立する段階です。友人や家族との連絡を避け、趣味や娯楽への興味を失います。自身の感情を閉じ込め、他者との関係が希薄になります。
例:SNSに依存。ゲームやスマホに逃げる。「勉強しなきゃ」という思いと現実逃避の間で葛藤。
⑧ 明らかな行動の変化 (Obvious Behavioral Changes)
→ これまでの段階で内面に蓄積されたストレスが、明確な行動の変化として現れる段階です。怒りっぽくなる、イライラしやすくなる、集中力の低下、無気力、不安感の増大などが見られます。
例:無表情、無関心、突然の不登校。周囲には「理由がわからない」と映る。
⑨ 人格の変化
→ 自己とのつながりが希薄になり、自分自身や周囲の現実に対して非現実感や疎外感を抱く段階です。感情が麻痺し、他者への共感能力が低下したり、冷淡になったりすることがあります。
例:明るく素直だった子が、怒りっぽくなったり、無口になる。「性格が変わった?」という声も。
⑩ 内的空虚 (Inner Emptiness)
→ 心の中に大きな空虚感を感じる段階です。何に対しても喜びや興味を感じなくなり、絶望感や虚無感に苛まれます。目的や意味を見出せず、生きている実感も薄れていきます。
例:「自分には何もない」「なぜ生きているのか」と感じる。自己否定が強まる。
⑪ うつ病 (Depression)
→ 重度のうつ病の症状が現れる段階です。気分の著しい落ち込み、不眠、食欲不振、疲労感、集中力や判断力の低下、自己肯定感の喪失、希死念慮などがみられることがあります。
例:やる気が出ない、涙が止まらない、死にたい気持ち…。この段階でようやくSOSが表面化。
⑫ 燃え尽き症候群 (Burnout Syndrome / Exhaustion)
→ 身体的、精神的、感情的に完全に消耗しきった最終段階です。心身の機能が著しく低下し、日常生活を送ることすら困難になります。緊急の医療的介入が必要となる場合もあります。
例:起き上がれなくなる。学校に行けなくなる。
バーンアウトの先にあるOD?
起立性調節障害は、自律神経機能や脳血流調整機能の破綻が関係している身体疾患です 。しかしそれを引き起こす、または増悪させる背景には、がんばりすぎる性格特性が深く関係しているように思います。
「病気になって初めて、自分が無理していたことに気づいた」
OD患児は、そう語ることがあります。
この燃え尽き症候群の12段階モデルは、あくまでモデルでありみんながこれに従って進行するわけではないですし、ODが燃え尽き症候群だというわけでもありません。
しかし、ODの過剰適応といった性格傾向では、無自覚に無理をして頑張りすぎることが往々にしてあります。
自分自身の心身の状態がどのような段階にあり、このまま無理を続けるとどういう未来が待っているのかを自覚するためにも、、、
また、見た目ではわからない「静かなSOS」に気づいてあげえれるためにも、参考になるのではないかと思います。
ではまた!


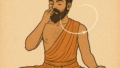
コメント