「雨が降ると体調が悪い」「曇りの日はなんだか頭痛や吐き気がひどい」こんなふうに感じたことはありませんか?私も天気や気圧の影響を受けることがしばしばあり、頭痛がするなと思ったら、その後に雨が降るといった具合に、体調の変化から天気の変化を感知することすらあります。
この天気(気圧)の変化は起立性調節障害(OD)の症状発現に深く関係しています。今回は、なぜ気圧の変化が体調に影響するのか、そしてそれにどう対応すればいいのかについてみていきます。
起立性調節障害と気圧の関係
起立性調節障害は、自律神経がうまく働かず、立ち上がったときなどに血圧調節がうまくいかなくなる病気です。これにより、脳や全身への血液循環が滞り、さまざまな症状があらわれます。
気圧とは、大気(空気)の圧力です。
気圧が下がると、体にかかる空気の圧力が減ります。これにより血管が拡張してしまいます。本来なら自律神経(交感神経)を働かせ、血管を収縮させ、血圧を保ちますが、ODではこの一連の自律神経活動がうまく働きません。その結果、血圧がさらに下がってしまうのです。
特に、梅雨や台風の時期、曇りや雨の日などは要注意です。これらの日は気圧が低く、ODの症状が悪化しやすいことが知られています。
どう対策すればいいの?
○気圧変化を見越したスケジュール調整
現在は天気予報だけでなく気圧の変化をしらしてくれるアプリが存在します。『頭痛ーる』というアプリは気象予報士が開発したもので、気圧変化による体調不良を予測してくれることに加えて、実際の体調を記録することのできる優れものです。自分の傾向を把握し、直近の気圧予報をチェックすることで、無理のないスケジュール調整ができるかと思います。キツい時には無理をせず休む勇気を持つことも大切です。
○水分・塩分の補給
血圧を安定させるには、体内の水分量を増やすことが基本です。そのために、こまめに水分を摂取し、合わせて塩分も少々摂取することで、血管内の水分(循環血漿量)も増加し効果的です。
○軽い運動も効果的
過度な安静(ゴロゴロや座りすぎ)は特に下肢の筋力を落とし、かえって症状を悪化させます(デコンディショニング)。体水分量と下肢筋力を維持するためにもウォーキングなどを取り入れ、寝転がっている時間を極力短くする工夫が必要です。
気圧変動とうまく付き合う
天候による不調は、“気のせい”ではありません。自律神経の働きが低下しているODでは、気圧の変化に対する適応がうまくいかないことで頭痛を始めとした身体の不調が出てきます。私自身、体育会系の人間が多い環境で過ごしてきたこともあり、天気を理由に休むなど言えない!といった思考が浮かぶことはあります。しかし、これまで見てきたようにODが気圧変動の影響を受けやすい理屈は理解できたと思います。体調の波があるのは当たり前。調子が悪い日は、「今日は天気が理由かな」と受け入れ、無理せず過ごしましょう。重要なのは、自分の体調に関するデータを集め、体と向き合い、極力ベストな状態に調整できるようになっていくことです。
ではまた!

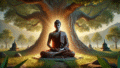

コメント